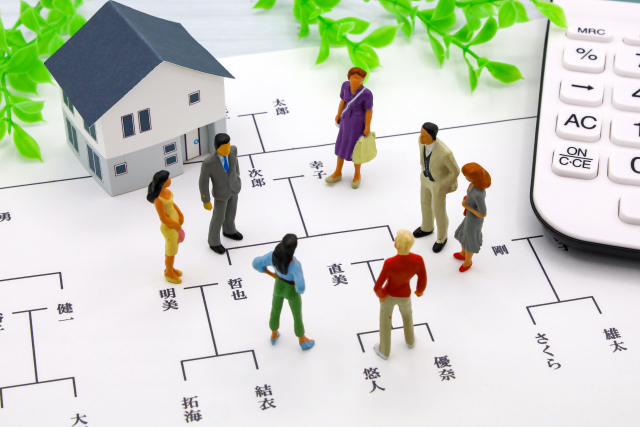家を整理するときに一番やっかいなのは、**モノの片付けより“人の気持ち”**です。
「売るのか残すのか」「誰が中心になるのか」「費用はどう分担するのか」──この答えが曖昧なまま進めると、家族の間で不満や誤解が生まれ、やがて大きなトラブルに発展してしまいます。
この記事を最後まで読めば、
- 家族で揉めずに話し合うための具体的な手順
- 本人の意思をきちんと残す方法
- 書類や情報を“見える化”して共有するコツ
- 誰が何を担当するのかを決め、必要に応じて専門家を入れる判断軸
が分かります。
つまり、「どう動けば家族で円満に家を整理できるのか」が、今日からすぐにイメージできるようになるのです。
家族会議を開く
事例
あるご家庭では、お父様が亡くなったあとに空き家になった実家をどうするかで、兄弟が真っ二つ。
長男は「思い出の家だから残したい」、次男は「維持費がかかるから早く売りたい」、三男は「とりあえず様子を見たい」。
結論が出ないまま2年が経ち、固定資産税は払い続け、庭は荒れ、ご近所から苦情も寄せられるようになってしまいました。さらに、相続から3年を過ぎてしまったため、「空き家特例」と呼ばれる税制優遇も使えなくなってしまったのです。
具体的な進め方
- タイミング
親が元気なうちに一度は必ず。入院や認知症発症後では手遅れになることも少なくありません。 - 参加者
相続人全員が理想。遠方に住んでいる人はオンライン参加でも構いません。 - 進め方
1. 議題をシンプルに「住む?貸す?売る?」に絞る
2. 感情論ではなく、維持費や相続税など“数字ベース”の話を中心にする
3. 脱線しないよう“司会役”を決める
本人の意思を確認する
事例
あるご家庭では、お父様が介護施設に入ることになり、実家をどうするかで兄妹が話し合うことになりました。
父親は「お前たちでよく話し合って決めてくれればいい」と言っていました。
一見すると子どもたちに任せる“円満な言葉”ですが、実はこれが大きな落とし穴。
長女は「父は残してほしいと思っているはず」、長男は「いや、売却して整理してほしいという意味だ」と、それぞれに“自分の解釈”をしてしまったのです。
本当は父親自身に「この家は〇〇に引き継いでもらいたい」という気持ちがあったのかもしれませんが、それが明文化されていなかったため、話は平行線に。やがて感情的な対立となり、家庭裁判所の調停にまで発展してしまいました。
具体的な進め方
- タイミング
親が判断できるうちに。入院後や認知症が進んでからでは、本人の意思確認ができず“空白”になりやすいです。 - 参加者
親+子ども全員が理想。本人の思いを正しく記録することが目的なので、できれば家族全員が立ち会って聞くのが望ましいです。 - 方法
1. 書面に残す(エンディングノートや遺言書が理想)
2. 難しければ、手書きのメモや家族宛ての手紙でもよい
3. 書面化が難しいなら、音声や動画で残しても効果あり - 注意点
「お父さんはこう言っていた」という口頭の伝聞は、一番揉めやすい。必ず形に残すことが大事です。
情報を共有する
事例
ある70代のお母様は、「大事な書類はちゃんと私が持っているから心配しなくていい」と言って、登記簿や固定資産税の通知書、権利証などをタンスの奥にしまい込んでいました。
ところが実際には、子どもたちが「見せてほしい」と頼んでも「どこにしまったか分からない」「これが何の書類かよく分からない」と言葉を濁すばかり。
母親としては「自分の代は自分で責任を持つ」という思いがあったのかもしれません。けれど、子どもたちからすると「本当に全部そろっているのか?」「大事なものを隠しているのでは?」と疑念が募り、兄妹の関係がギクシャクしてしまいました。
実際には母親が悪気を持っていたわけではなく、単に“分からないまま抱え込んでいた”だけ。けれど、この「情報の不透明さ」が家族に不信感を生み、トラブルの火種になったのです。
具体的な進め方
- タイミング
親がまだ元気で判断できるうちに。本人が入院したり、認知症が進んでからでは探し出すのが困難になりがちです。 - 共有すべき書類
- 登記簿謄本
- 固定資産税通知書
- 権利証または登記識別情報- 修繕履歴や管理組合資料(マンションの場合)
- 共有方法
1. コピーやスキャンをとって、子どもたち全員が見られるようにする
2. 紙で配るより、クラウド(GoogleドライブやDropboxなど)にまとめる方が効率的
3. ITが苦手な家族がいる場合は、LINEグループに写真を送るだけでも十分 - 注意点
一人で抱え込まないこと。情報をオープンにして、「誰でも確認できる状態」にしておくことが、兄妹の信頼関係を守る最大のポイントです。
役割分担と専門家活用
事例
あるご家庭では、相続した実家の処分について「誰が手続きを進めるのか」を決めないまま放置してしまいました。
兄は「弟が不動産関係に詳しいからやってくれるだろう」、弟は「長男なんだから兄が主導するはず」と、お互いに“相手任せ”。
結果、誰も動かないまま1年が過ぎ、買い手がつきやすいタイミングを逃してしまいました。
その後は市場が冷え込み、結局は当初よりも数百万円も安い価格で売却することに…。
具体的な進め方
- タイミング
家族会議や意思確認の場で、必ず「代表者(窓口役)」を決めておく。後から決めようとすると揉めやすい。 - 役割分担の決め方
- 売却や解体の手続きは誰が窓口になるのか- 固定資産税や管理費の支払いは誰が負担するのか
- 書類の保管・情報整理は誰が担当するのか
- 専門家の活用
- 不動産会社:査定や売却活動のサポート- 司法書士:相続登記や名義変更の手続き
- 税理士:譲渡所得税や相続税の試算
- 行政書士や弁護士:家族信託や遺産分割協議での合意形成
- 注意点
家族だけで解決しようとすると感情が先に立ちやすい。行き詰まったら早めに第三者を入れることで、スムーズに話が進むケースが多い。
まとめ
家族で揉めずに整理を進めるには、結局のところ 段取り がすべてです。
- 家族会議 早い段階で全員が集まり、方向性を話し合う
- 意思確認 本人の思いを“形に残す”
- 情報共有 書類を整理して誰でも確認できる状態にする
- 役割分担と専門家活用 窓口を決め、必要なら第三者の力を借りる
これらを押さえておくだけで、後のトラブルの8割は防げます。
「親を思って言ったはずの一言が火種になる」──そんな悲しい事態を避けるためにも、元気なうちに一度は家族でテーブルを囲んでみてください。
あとでやろうは、もう遅い。
「今ならまだ間に合う」という視点を、ぜひ持っていただければと思います。
次回予告
次回・第4話は、「専門家をどう使うか」 がテーマです。
家族だけで解決しようとすると感情的になりがちですが、司法書士・不動産会社・税理士などの専門家をうまく活用することで、驚くほどスムーズに進むケースがあります。
「どのタイミングで」「どんな専門家に」頼むのがベストかを、具体的に解説していきます。